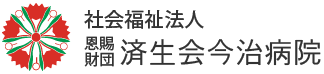本文
透析センター
透析センター


透析センターの概要
ベッド数
73床(72台はオンライン血液ろ過透析:OHDF対応) 内個室3床あり
スケジュール
| 1部 | 2部 | 夜 | |
|
月 水 金 |
【Cブース】20床 8:30~開始 |
【Aブース】28床 9:45~開始 【Bブース】25床 9:20~開始 |
【A・Cブース】 17:00~ 4時間透析開始 16:30~ 5時間透析開始 |
|
火 木 土 |
- |
🔷1部・2部Bブースは曜日とベッド位置による順番穿刺を試みています
🔷ベッド場所は治療上の都合により変更する場合があります
治療
血液透析(HD)、血液透析濾過(HDF、on-lineHDF)など
※腹膜透析(CAPD)の治療・管理は行っておりません。
その他:血液浄化
血漿交換、血液吸着、持続的血液透析濾過、腹水濾過濃縮再静注など
特色
・超音波エコー下にてガイド穿刺を行い、穿刺困難な患者様のストレス軽減に努めています。
・6時間までの長時間透析に対応しています。
・除水制限を設けています。
・看護師・臨床工学技士による各チーム活動にて個別性に応じた看護、治療の提供に取り組んでいます。
・徹底した水質管理を行っています。
・他科(栄養科・リハビリテーション科・各認定看護師)との連携により合併症の予防・早期発見に積極的に努めています。
・腎臓内科専門医(非常勤)による回診・面談があります。
・定期的な血液検査以外に体液量測定・骨密度検査・シャントエコ-・胸腹部CT等を行っています。
・透析中の運動療法や栄養士により栄養指導を行っています。またシャントトラブルにも対応しております。
・病院運営の無料透析送迎バスで対応できる地域なら送迎可能です。(単独行動可能な方)
治療や臨時透析など詳細は以下にお問い合わせください
臨時透析をご希望の方は、13:00~16:00までの間にお電話にて問い合わせください。
TEL (0898)47-2500
FAX (0898)48-5096
水質管理について
透析療法において、透析液は必要不可欠です。1回の治療で1人あたり120~150L程必要とし、当院では1日当たり100名以上の患者様に使用します。なので、これに応じて大量の透析用水が必要になります。
当院の透析用水は、井戸水や水道水を使用しています。これらの中には、微小なゴミやバクテリア、不要な電解質、残留塩素などが含まれ、透析用水として使用するには、これらを取り除く必要があります。濾過やイオン交換、吸着、逆浸透などの原理を用いこれらを取り除きます。また代表的な不純物の1つにエンドトキシンというものがあり、透析液から流入する事で、発熱や血圧低下などの症状を引き起こす危険性があります。そのため、ETRF(エンドトキシン捕捉フィルター)を全監視装置に装着しています。また定期的に透析液中の細菌とエンドトキシンを測定し安全な透析液を提供できるように努めています。
透析ってどうしてするんでしょうか?
腎不全・透析療法について
腎臓の働き
腎臓には心拍出量の1/4の血液が流れ、血液を濾過し、過剰な水分や老廃物の排泄、ナトリウムやカリウムなどの電解質の調整、酸塩基平衡の調節、血圧を調整するホルモンや赤血球を作るのに必要なホルモンの分泌、ビタミンDの活性化など、大変重要な働きをしています。
腎臓が悪くなると
腎臓の機能が低下してくると、腎臓は老廃物や水分を十分に排泄できなくなり、過剰な水分や有害な物質が蓄積してきます。
血液検査では、貧血や尿素窒素・クレアチニン・リンなどが上昇し、血液が酸性になってきます。
腎臓の機能が30%以下になると、食欲不振・吐き気・おうと・全身倦怠・貧血・むくみ・高血圧・神経症状などが現れます。
さらに進行し末期になると、意識障害・昏睡・肺水腫・高カリウム血症など生命に重篤な影響を及ぼします。
治療
末期腎不全の治療には、血液透析・腹膜透析・腎移植があります。もっとも普及している治療が血液透析で、全国で33万人近い方が治療を受けています。医療の進歩に伴って、血液透析を導入される年齢が高齢化し、治療も長期化している傾向にあります。そのため合併症を起こすことなく、長く病気に付き合っていく治療や自己管理が重要になっています。 腎臓移植についてご希望のある方は、ご相談ください。
血液透析について
血液透析は本来腎臓で行われる老廃物の排泄や体液量の調節、電解質や酸塩基平行の調節を機械的に行う方法です。
通常、血液を取り出しやすくするために外科的に静脈と動脈をつないだ「シャント」を作成します。
このシャントに針を刺し、血液を取り出して、ダイアライザーと呼ばれる人工腎臓に血液を通し体に返します。
この一連の流れを連続して行うことにより、老廃物や過剰な水分を除去し、また不足している電解質などを補給して、体液を正常に近づけます。
この治療は1回4~5時間、週に3回行うことが必要です。
透析時間について
健康な腎臓は24時間休みなく働いて血液をきれいにし、余分な水分を尿として排出しています。透析治療はその腎臓の代わりをしており、ほとんどの方が週3回、4時間~5時間の透析治療を行っています。1回の透析時間が長いと生命予後が良いとの報告がされおり、当院では、できるだけ長い時間の透析を患者様にお勧めしています。ご希望があれば6時間透析も可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。
超音波エコー穿刺について
血液透析療法では体から血液を取り出すためのルートと、治療で正常に近づいた血液を体に戻すためのルートの2本の針を刺すことが透析の度に必要となり、透析治療において患者様の最大の苦痛となります。
一般的には、血管を触って確認してから針を刺すこと(穿刺)が必要となりますが、血管が細い、触ってもわかりにくい場合などではうまく穿刺が出来ないことがあります。
当院ではその様な穿刺困難な患者様のために超音波エコー使用した穿刺を県内でも早期に導入しております。エコー画像を活用することで血管径・深さ・血管内部を確認しながらリアルタイムで穿刺を行うことができるため、穿刺ミスの確率を下げることが可能となっております。


除水制限について *当院は除水制限を設けております
除水は透析療法の大きな目的の一つです。患者様に負担が少ない理想的な除水量は、透析日が1日空きの場合は基礎体重(ドライウエイト)の3%以内、2日空きの場合は、5%以内とされています。しかし、3%~5%(ドライウエイト50㎏の方で1500ml~2500ml)は大変厳しいと思われる患者様も多いのではないでしょうか?
当院では3%~5%を目標としていますが、患者様の体格・年齢・合併症・心胸比等をふまえて、患者様に合った除水量を決定しています。ただ、体の大きい患者様(約80㎏)でも1時間当たり800mlまで、40kg以下の患者様は600mlまでの除水とさせて頂いております。
患者様にとって、体に溜まった余分な水分を取り除くことは重要な治療です。しかし、多すぎる除水は体に負担がかかるため、日頃から体重管理を意識するようにしてください。除水は適切な量とスピードで行うことが大切です。
チーム活動
条件チーム
チームメンバーにて、採血結果をもとに患者様により良い透析治療を提供できるよう、注射・内服薬の変更などの検討を主治医へ相談を行っています。透析センターの看護師が毎月の検査の結果をもとに、食事内容の確認、内服状況の確認を声かけさせていただくこともあると思いますが、ご協力お願い致します。
バスキュラーアクセス管理チーム
バスキュラーアクセスとは血液透析を行う際に、血液を脱血したり、返血したりするためのアクセスルートで透析患者様には必要不可欠なものです。
チーム活動の一環としてバスキュラーアクセスが長期間維持できるように、シャントトラブルの予防と早期発見に努めています。
特に夏場は、シャントを長持ちさせるためにも、脱水によるシャントの閉塞・狭窄・感染への予防に心がけ、患者様ご自身でも自己管理に十分気をつけてください。気になることがありましたら、いつでもスタッフにお知らせ下さい。
DM(糖尿病)・スキンケアチーム
糖尿病の3大合併症に腎症・網膜症・末梢神経障害があります。
透析患者様の半数は糖尿病による腎症で透析治療を余儀なくされています。網膜症により目が不自由になると見ることができない、末梢の感覚が鈍くなると、傷ができた事にも気づかず悪化させてしまう事もあります。また、透析歴が長くなると血管の石灰化が起こりやすく、血管の弾力が低下し閉塞性動脈硬化症を発症しやすくなります。
そこで、毎月足の動脈を触わって観察し、足病変の早期発見、予防に努めています。2020年8月下肢潰瘍の改善を目的とした治療、血液浄化療法(レオカーナ)が承認され、2021年12月より当院でも治療を開始しています。まだまだ症例件数は少ないですが、潰瘍が改善し、少しでも苦痛が緩和し日常生活が送れるようにサポートできたらと、多職種と連携し取り組んでいます。
何かスキントラブルやお困りの事がありましたらスタッフまでお知らせ下さい。
(レオカーナによる血液浄化)
サルコぺニアチーム
サルコペニアとは加齢や疾患により筋肉量が減少することで、全身の筋力低下または身体機能が低下することです。 転倒やふらつきなどの原因になり、寝たきりになる可能性も出てきます。シニアの低栄養やサルコペニアを起因として疲労、活力低下、筋力低下から身体機能の低下、活動の低下につながり「加齢により心身が老い衰えた状態」をフレイルと言います。
サルコペニアと骨粗鬆症は関連しており、サルコペニアそのものが骨粗鬆症と骨折の危険因子といわれています。また透析治療中の4~5時間の無運動状態がサルコペニア・フレイルを加速させる要因にもなります。
2022年度から順次、骨密度検査を実施、結果より骨粗鬆症治療を開始しています。また透析導入3ヶ月以降の患者様へ運動療法の働きかけも行っています。
ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を維持し、いつまでも自宅から透析に通える手助けができたらと考えています。運動療法を是非やってみたいとお考えの方は、スタッフまでお知らせ下さい。
透析中の運動療法

CKD外来(ACP)チーム
外来や総合医療支援室・病棟と連携し、透析導入前から透析導入後までの継続した看護を提供できるよう活動しています。
慢性腎臓病について理解を深め、円滑な治療が継続できるよう支援していきます。
『人生会議』 ACP(アドバンス(A)・ケア(C)・プランニング(P))という言葉はご存知でしょうか?
医療従事者と、患者様・ご家族様とこれからの治療やケアについて話し合いを重ねていくプロセスの事です。患者様の価値観・意向を尊重した支援が行えるよう関わっていきたいと考えています。相談したい事やちょっとお話したいことがあれば、いつでもお知らせ下さい。
災害チーム
いつ起こるか分からない災害に対して、備える活動をしています。当院で行っている災害対策を紹介させていただきます。
災害カード
患者様各自の透析条件を記入したカードを毎月更新しお配りしています。災害などの緊急時他院で透析治療を受ける場合に必要です。
緊急連絡先の確認
年度初めに確認を行っています。安否確認や透析の有無などを連絡する際に必要です。
赤札(体重測定カード裏)
車いすを利用されているなど、自力で移動できない患者様の体重カード裏には赤いテープを貼っています。避難の際、誰が助けを必要としているか一目で分かる様にしています。
防災訓練の実施
透析中の緊急離脱や地震時の対応など、患者様参加型の防災訓練を適宜行っています。
災害時透析拠点病院の役割
災害時の水や電源の確保、ダイアライザーや透析回路の備蓄。今治市内における透析病院やクリニックとの定期的な情報交換を行い、災害時に迅速に対応できるようにしています。
医療安全推進チーム
患者様も安心・安全な透析治療をうけていただけるよう環境や医療体制を整えるよう努めています。重大事故防止に向けた取り組みを始め、転倒やシャント感染の予防、集団院内感染防止のため、スタッフ全体で協力しています。また、体調不良等の変化に注意し早期に対応できるよう各部署との連携を図るようにしています。
透析センター便り そら豆
Vol.35 1月号 2026.1 [PDFファイル/4.69MB]
Vol.34 運動推進号 2024.5 [PDFファイル/770KB]
Vol.33 防災号 2024.1 [PDFファイル/1.46MB]
Vol.31 梅雨号 2023.6 [PDFファイル/895KB]
Vol.30 号外 2022.7 [PDFファイル/538KB]
Vol.29 夏号 2022.6 [PDFファイル/733KB]
vol.28 迎春号 2022.1 [PDFファイル/724KB]
vol.27 夏の増刊号 2021.8 [PDFファイル/647KB]
vol.26 5月号 2021.5 [PDFファイル/573KB]
vol.25 1月号 2021.1 [PDFファイル/952KB]
vol.24 9月号 2020.9 [PDFファイル/671KB]
vol.23 5月号 2020.5 [PDFファイル/735KB]
Vol.22 冬号 2020.1 [PDFファイル/766KB]
vol.19 冬号 2019.3 [PDFファイル/776KB]
vol.18 秋号 2018.10 [PDFファイル/708KB]
vol.17 夏号 2018.7 [PDFファイル/898KB]
vol.17 増刊号 2018.6 [PDFファイル/570KB]
vol.16 春号 2018.4 [PDFファイル/820KB]
vol.14 秋号 2017.10 [PDFファイル/763KB]
vol.13 夏号 2017.7 [PDFファイル/807KB]
vol.12 春号 2017.4 [PDFファイル/1.02MB]
vol.11 冬号 2017.1 [PDFファイル/822KB]
vol.10 秋号 2016.10 [PDFファイル/816KB]
vol.9 夏号 2016.07 [PDFファイル/897KB]
vol.6 秋号 2015.10 [PDFファイル/918KB]
vol.5 夏号 2015.07 [PDFファイル/545KB]
vol.4 春号 2015.04 [PDFファイル/1.18MB]
vol.3 冬号 2015.01 [PDFファイル/652KB]
vol.2 秋号 2014.10 [PDFファイル/825KB]